
自動車の第二種免許を取得して、プロのドライバーとして新たなキャリアを目指す方も少なくありません。しかし、そのためにはどの運転免許を取得すればよいのかが分からないという方もいるでしょう。そもそも「第二種免許ってなに?」「どうやって取得するの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では第二種免許の基礎知識や合宿免許でどのような教習を経て第二種免許を取得するのか、免許取得までの期間や費用などを詳しく解説します!さらに、合宿免許のメリットや通学免許との違いなどについても紹介します。ぜひ参考にしてください。
関連記事:指定自動車教習所とは? メリットや運転免許取得までの流れを解説
※合宿免許さぽっとでは普通免許(AT/MT)のプランのみ申し込めます
目次
第二種免許とは

第二種免許とは、“仕事としてお客様を運ぶために必要な免許”であり、“人を乗せて運び、運賃をもらう”業種において必須の免許です。具体的には、旅客自動車を運転する場合や普通自動車を運転するケースでも運転代行業の場合には、第二種免許が求められます。
第二種免許は、商業目的のドライバーとして取得しなければならないため、人を運送する目的であっても送迎バスやシャトルバスなどの運賃が発生しない自家用車には必要ありません。ただし、これはバス会社に委託せずに自社サービスの一環で運行する場合です。
第二種免許を取得するメリット

第二種免許を取得することで、幅広い分野でのキャリアアップが期待できます。また、安定した収入を得られるだけでなく、社会貢献にもつながります。
例えば、以下のような職業に就くことができます。
- タクシー運転手
- バス運転手
- 運転代行業
- 介護タクシーの運転手 など
さらに、教習を通して安心・安全に旅客を送迎できる技術や旅客への配慮など、多角的な視点での専門的な知識も学べるため、自己成長にもつながるといったメリットもあります。
第二種免許の種類
第二種免許には『普通第二種免許』『中型第二種免許』『大型第二種免許』『大型特殊第二種免許』『牽引(けん引)第二種免許』があります。これらの免許がどのようなものなのか、どのような車種を運転できるかなどを解説します。
普通第二種免許

普通第二種免許を取得するとタクシーや介護タクシー、ハイヤー、代行によるお客様の自動車などを運転できます。
具体的には、以下の3項目を満たした普通自動車で旅客運送が可能です。
- 車両総重量5t未満
- 最大積載量2t未満
- 乗車定員10人以下
普通第二種免許では、MT免許とAT限定免許を取得できます。MT免許での取得を考えている方で、現在第一種免許の普通車免許(AT)を持っている場合は、先にAT限定解除を行うことをおすすめします。もちろんクラッチ操作などの教習はありますが、ただでさえ難易度が高いためMT車での運転には慣れているに越したことはありません。
「普通車免許を持っているのにまた学科教習があるの?」と思う方もいるかもしれませんが、
第一種免許と第二種免許では学科教習内容が異なります。合格率も第一種ほど高くないため、より一層勉強の時間を設けることが大切です。
中型第二種免許
中型第二種免許では、以下の3項目を満たした中型自動車での旅客運送が可能です。
- 車両総重量5〜11t未満
- 最大積載量3〜6.5t未満
- 乗車定員11〜29人
中型第二種免許を取得すると、緑色のナンバープレートの車両を運転できます。
具体的には以下の車両が該当します。
■緑色のナンバープレート
- 送迎バス(マイクロバス)
- 観光バス(中型タイプ・貸切バスなど)
- タクシー
中型第二種免許の場合、現在の所有免許が第一種免許の中型8t限定またはAT限定免許の方は、事前に限定解除をしておく必要があります。
大型第二種免許

大型第二種免許とは、路線バスや観光バスなど乗客を乗せて運行する大型車両の運転に必要な運転免許です。具体的には、以下の3項目を満たした大型自動車での旅客運送が可能です。
- 車両総重量11t以上
- 最大積載量6.5t以上
- 乗車定員30人以下
大型第二種免許を取得すると、以下の車両を運転できます。
- 大型バス
- タクシー、ハイヤー、運転代行での普通自動車 (普通第二種免許に該当する車両)
- マイクロバスでの旅客運送 (中型第二種免許に該当する車両)
- 大型トラック、ダンプカーなど (旅客を伴わない大型第一種免許に該当する車両)
- 中型自動車
- 普通自動車
- 小型特殊自動車
- 原動機付自転車
大型第二種免許は、乗客の安全を第一に考え、高い運転技術と安全意識が求められるため、運転免許の中でも難易度が高い免許の一つとされています。
大型特殊第二種免許
大型特殊第二種免許とは、乗客を乗せて運行する大型特殊自動車の運転に必要な運転免許です。具体的には、以下の車両が挙げられます。
- 旅客運送用の雪上バス・雪上車(スキー場や雪山などの積雪地で運行)
- フォークリフト(旅客運送事業に使用する場合)
- ショベルカー(旅客運送事業に使用する場合)
- 除雪自動車(旅客運送事業に使用する場合)
※フォークリフトやショベルカー、除雪自動車などは大型特殊自動車に該当しますが、旅客の運送に使うことはほとんどありません。
大型特殊第二種免許は特殊形状の車両が対象であり、教習で学ぶ内容が大型第二種免許とは異なります。そのため、大型特殊第二種免許を所持しているだけでは、大型自動車の運転はできません。
牽引(けん引)第二種免許
牽引第二種免許とは、牽引装置を持つ車両で車両総重量が750㎏以上の重量物を牽引し、かつ旅客を運送する際に必要な免許です。具体的には、トレーラーバスのような連結式のバスを牽引して運転する場合に必要です。しかし、現在の日本では旅客運送用の連結式バスは運行していないため、牽引第二種免許が必要になる場面は非常に限られています。
牽引する車両(トレーラーヘッド)を運転するためには、牽引免許だけでは車両の運転はできません。牽引する車両の種類や大きさに適合した免許の所持が必要です。
牽引第二種免許では、大型トレーラーやタンクローリーなども対象車両に当てはまりますが、大型特殊第二種免許と同様に使用機会が稀であるといえるでしょう。
第二種免許の取得条件

第二種免許の取得条件は、第一種免許よりも受験資格が厳しく設定されています。はじめて運転免許を取得する方や第一種免許所持者でも運転経験のない方、運転経歴の浅い方が第二種免許を取得することはできないため、あらかじめ注意が必要です。
ここからは、普通、中型、大型の3種類に絞って、第二種免許を取得するための条件を解説します。
■第二種免許の取得条件
| 条件 | 詳細 |
| 年齢 | 満21歳以上 ※19歳以上で所定の条件(受験資格特例教習修了+所持免許期間1年以上)を満たせば受験可能 |
| 運転経歴 | 普通自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許、大型特殊自動車免許のいずれかの第一種免許所持期間が通算して3年以上であること ※免許取消や免停処分期間を除く ※けん引第二種は第一種けん引免許も必要 |
| 視力 | 両眼で0.8以上かつ片眼でそれぞれ0.5以上であること(眼鏡、コンタクトレンズの使用可) ※色付きメガネや遮光メガネ、カラーコンタクトレンズなどを除く |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができること |
| 深視力 | 三桿法を使った3回の深視力検査で、誤差が平均2㎝以下であること |
| 聴力 | 10mの距離で90dB(デシベル)の警音器の音が聞こえること(補聴器の使用可) |
| 運動能力 | 自動車運転に支障を及ぼす恐れのある身体障がいがないこと |
身体的に心配のある方は、住民票に記載された住所を管轄する各都道府県の『運転免許試験場(運転免許センター)の安全運転相談(運転適性相談)窓口』に相談してください。
第二種免許の取得方法
第二種免許の取得方法は、 大きく2つに分けられます。これらの方法を詳しく解説します。
教習を受けず試験で一発合格を狙う

1つ目は、指定教習所で教習を受けずに、直接運転免許試験場で一発試験を受験する方法です。
項目別に詳しく見てみましょう。
概要
教習所に通う時間がとれない方や柔軟なスケジュールで免許取得を目指したい方などに合った受験方法です。大型特殊第二種免許と牽引第二種免許では、教習所で受け入れているプランがほとんどないため、この方法で免許取得を狙う必要があります。
試験内容
一発試験では学科試験の合格後に、適性試験、技能試験(場内・路上)が行われます。対象車両を路上で運転できるように事前に第一種免許を取得しておく必要があります。所有免許が第一種免許のみの場合は、学科試験も合格しなければなりません。
学科試験では、文章問題90問とイラスト問題5問の合計95問からなり、合格基準は90点以上です。技能試験は、場内ではS字やクランク、方向転換や縦列駐車など、路上では乗客を想定した正確かつ安全な運転が求められ、どちらも減点方式で80 点以上が合格ラインです。
受験費用
一発試験の費用は、以下のとおりです。
| 項目 | 区分 | 金額 |
| 受験料 | 大型・中型・普通第二種免許 | 4,500円 |
| 大型特殊・牽引第二種免許 | 2,800円 | |
| 試験車使用料 | 共通 | 2,950円 |
| 免許証交付料 | 通常の免許証のみ | 2,350円 |
| マイナ免許証のみ | 1,550円 | |
| 両方同時取得 | 2,450円 | |
| 取得時講習受講料 | 旅客車講習 | 19,200円 |
| 旅客応急救護処置講習 | 11,100円 | |
| 合計 | 30,300円 |
一発合格の取得方法に適した方
一発試験の合格率は非常に低く、すでにほかの第二種免許を取得している方でも、合格の難易度は高いといわれています。十分な運転経験を持ち、運転を得意としている方であれば合格率は高まりますが、それでも一発試験に挑戦する場合は、十分な準備と対策が必要です。そのため、教習所で着実に運転技術を学んだうえで受験するほうが合格の可能性が高まります。
通学・合宿免許を利用する

2つ目は、教習所で教習を受ける方法です。これには、自宅から通学する『通学免許』と、教習所が用意した宿泊施設に滞在しながら教習を受ける『合宿免許』の2つの方法があります。
ここでは、通学免許と合宿免許について説明します。
通学・合宿免許の違い
どちらも一発試験と異なり、指導員に知識や技術などを教わりながら適切な運転スキルを身につけられます。
通学は自宅や仕事場から近い教習所に通って受けられるため、自分の都合に合わせて通えます。平日や休日を自由に選べる反面、都度教習の予約を入れる必要があり、卒業までに時間がかかりやすい点がデメリットといえます。
合宿免許は、教習所が提供する宿泊施設に滞在し、短期間でカリキュラムをこなします。日程はあらかじめ決められており、通学に比べて取得までの日数が短いのが特徴です。
合宿免許のメリット
合宿免許は、短期間で集中的に教習を受けられるため、忙しい社会人の方や効率的に免許を取得したい方に適しています。また、宿泊代や食事代などが含まれているプランが多く、通学に比べて費用を抑えられるというメリットもあります。さらに、自由時間を利用して周辺の観光スポットへ出かけたり、温泉につかったり、ほかの受講生と交流したりするなど、充実した合宿生活も送れます。
プラン料金はシーズンによって費用が変動するため、事前にしっかりと比較検討することが大切です。
教習所の種類
教習所はほかにも自動車学校や自動車教習所、ドライビングスクールやモータースクール、ドライバーズスクールなどさまざま名称がありますが、都道府県公安委員会が指定した”指定教習所”であれば、すべて同様の教習内容を受けられるため安心です。
ただし、取得免許の種類ごとに学科教習と技能教習の時限数に違いがあります。所持免許の種類によっては学科教習が免除になる場合もあります。あらかじめ確認しておきましょう。
合宿免許で第二種免許を取得するには

合宿免許で第二種免許を取得するには、取得期間や費用を理解しておくことが重要です。項目別にそれぞれを詳しく見てみましょう。
取得までの期間
合宿免許での第二種免許取得期間は、現在所持している免許の種類によって異なります。免許の種類別の取得期間は、以下のとおりです。
■普通第二種免許
| 時限・期間/所持免許 | 普通免許(AT・MT) | 大型・中型・準中型免許 |
| 技能教習 | 21時限
※普通免許ATの所持者が、MTを取得する際は25時限 |
18時限
※中型免許ATの所持者が、MTを取得する際は22時限 |
| 学科教習 | 19時限 | 19時限 |
| 最短日数 | 8~11日 | 7~9日 |
■中型第二種免許
| 時限・期間/所持免許 | 普通免許(AT・MT) | 準中型免許 | 大型・中型免許 |
| 技能教習 | 28時限
※普通免許ATの所持者が、MTを取得する際は32時限 |
24時限 | 18時限 |
| 学科教習 | 19時限 | 19時限 | 19時限 |
| 最短日数 | 約13日~ | 約12日~ | 約7日~ |
■大型第二種免許
| 時限・期間/所持免許 | 普通免許(AT・MT) | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 技能教習 | 34時限
※普通免許ATの所持者が、MTを取得する際は38時限 |
30時限 | 24時限 | 18時限 |
| 学科教習 | 19時限 | 19時限 | 19時限 | 19時限 |
| 最短日数 | 約16日~ | 約15日~ | 約11日~ | 約7日~ |
上記のとおり、普通第二種免許の最短日数は7泊8日~です。技能教習が21時限・学科教習が19時限あります。中型二種免許では、中型免許を所持している場合は6泊7日~です。普通免許(MT)を所持している場合は、学科教習が19時限・技能教習が28時限あり、仮免試験も行われます。日数は12泊13日~です。
すでに大型免許を所持している場合、ほかの所持免許と比べて技能教習の時限数が少なく最短で取得可能です。普通免許から大型第二種免許を取得する場合には、技能教習の時限数が最も多く取得までの期間も最長です。
学科教習の時間は、免許の種類にかかわらず同じです。普通・中型・大型の第二種免許では、所持免許がAT限定の場合、あらかじめ限定解除する必要があります。
なお、上記はあくまでも一般的な取得期間であり、教習所規定の最短日数や個人の進捗状況などによって変動します。
また、警視庁『普通第二種免許に係る教習カリキュラムの見直しについて』によると、2025年9月から教習時限が以下のように大幅に短縮される予定です。
学科教習:19時限→17時限
技能教習:21時限→12時限
これにより、最短教習日数も6日から3日に短縮される見込みです。
取得にかかる費用
第二種免許取得にかかる費用は、所持免許の種類に基づいて決められます。
所持免許による費用の変動
各費用の一般的な目安は、以下のとおりです。
■普通二種免許
| 所持免許 | 合宿免許 |
| 普通免許MT | 約20万円~ |
| 大型、中型、準中型免許 | 約19万円~ |
■中型二種免許
| 所持免許 | 合宿免許 |
| 普通免許MT | 約42万円~ |
| 準中型免許 | 約38万円~ |
| 大型、中型免許 | 約26万円~ |
■大型二種免許
| 所持免許 | 合宿免許 |
| 普通免許MT | 約40万円~ |
| 準中型免許 | 約40万円~ |
| 大型、中型免許 | 約27万円~ |
上記のとおり、大型免許を所持している場合には、技能教習の時限数が少ないため取得費用が安い傾向です。普通免許から第二種免許を取得する場合には、取得費用が特に高額です。
上記はあくまでも概算であり、シーズンやプランによって費用は異なります。別途、受験手数料や教材費などがかかる場合があります。合宿免許の場合は、交通費や個人的な諸費用も必要です。
教育訓練給付金制度の活用
大型自動車免許や第二種免許など仕事に活かせる運転免許を取得する際、教育訓練給付金制度を利用することで、費用の還付を受けられます。
これは、厚生労働省が労働者の能力開発を支援するために設置した『教育訓練給付制度』です。雇用保険の被保険者または被保険者だった場合に一定の条件を満たせば、運転免許取得費用のうち教習費用の20%(最大10万円まで)が戻ってきます。
合宿免許の費用を抑えたい方や費用の問題で免許取得を諦めていた方は、ぜひこの制度を活用してみてください。
詳しくは、厚生労働省のサイト『教育訓練給付制度』にてご確認ください。
取得の流れ
合宿免許で第二種免許を取得するまでの一般的な流れは、以下のとおりです。
1.第一段階
規定時限数の技能教習と学科教習を受けます。
2.修了検定
第一段階の最後に、修了検定を受験し合格すれば仮免許証が発行されます。
3.第二段階
規定時限数の技能教習と学科教習を受けます。第二段階からは路上教習があります。
4.卒業検定
規定時限数の技能教習と学科教習を修了し、卒業検定を受験します。
5.卒業
卒業検定に合格すると、晴れて卒業です。
6.本免許試験
合宿免許を卒業後、運転免許センターで本免許試験と適性試験を受け、合格すると免許証が交付されます。
難易度の高い試験にも対応! 合宿免許の保証制度
第二種免許の試験は合格基準が厳しく、最短期間よりも日程が長引くこともあります。合宿免許では、再受験や補習が必要になっても、規定の範囲内で費用が無料になる保証付きプランがあります。
ただし、保証制度を利用する際は注意点があります。例えば、ホテルやシングル、ツインの部屋に滞在していた場合でも、延泊時には相部屋へ移動することがあります。宿泊先が異なる宿舎に変わるケースもあり、選択が制限されることもあります。
延長以降は、昼食や夕食などで追加料金が発生する場合もあるため、申込前にどこまで費用に含まれるのかを確認しておくことが大切です。
“人の命を預かる”第二種免許は合宿免許の利用で安心!
第一種免許に比べて、第二種免許は『プロライセンス』で、試験や検定の合格ラインも高く設定されています。旅客が安心して利用できるように安全運転の高度な技術が求められ、旅客への配慮などを身につける必要もあります。これらの専門的な知識と技術は、独学では非常に難しいため、教習所での教習が最善策といえます。
教習所は、通学よりも合宿免許で短期集中して取得まで一気に行く方がおすすめです。第二種免許はストレートでの取得が難しいといわれているからこそ、自動車運転のプロである指導員から直接しっかり学ぶことが重要です。短期間で効率よく運転技術・免許を取得したい方は、連休や有休などを利用して合宿免許に申し込んでみてはいかがでしょうか。
ぜひ、自分に合った教習所を見つけて第二種免許取得に向けてがんばりましょう!
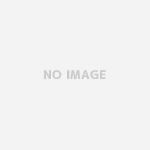

を取得するメリットと注意点-150x150.jpg)