
合宿免許を検討していると、自動車教習所のパンフレットや予約サイトで『適性検査』という言葉を目にすることがあるかもしれません。 しかし、この検査が具体的に何を目的とし、どのような内容なのか分からず、不安を感じる方もいるでしょう。
「適性検査で悪い結果が出たらどうなるのか?」 と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、適性検査は運転免許の取得に必要な基準を確認するためのものです。
そこで、本記事では合宿免許で実施される適性検査の目的や内容、検査結果の活用方法について解説します。
目次
合宿免許で受ける適性検査とは
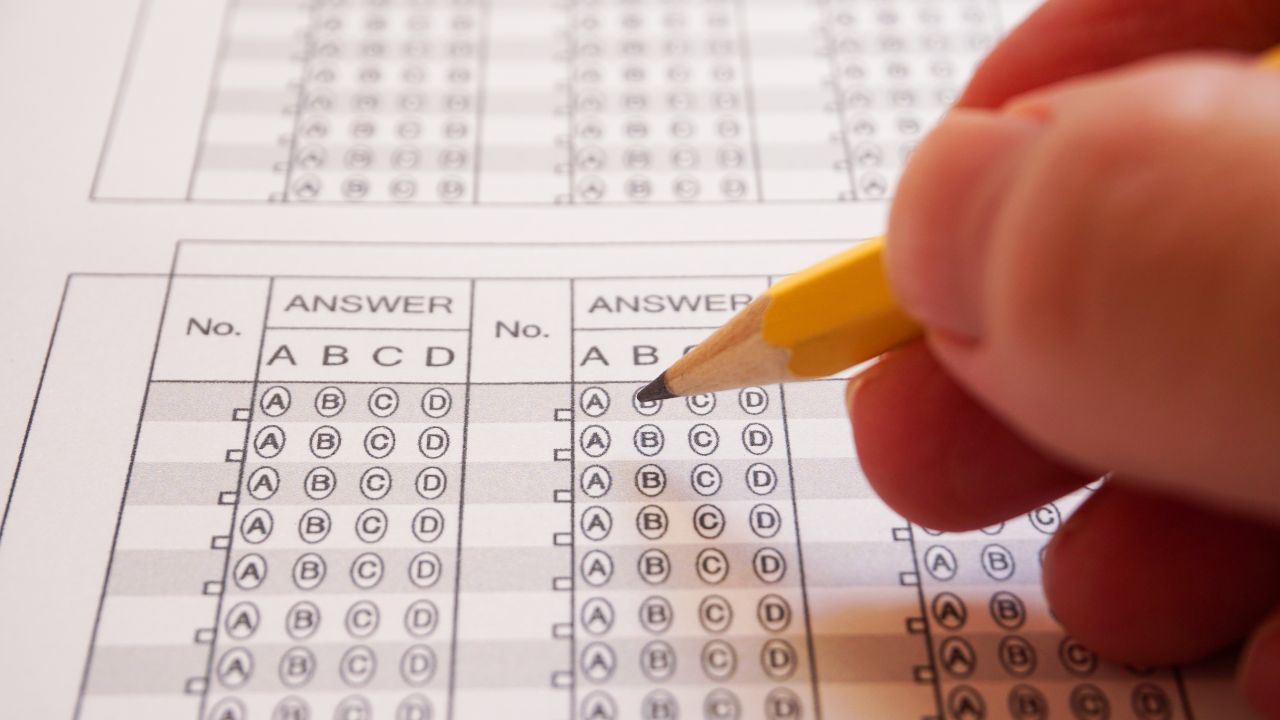
適性検査とは、運転免許を取得する際に必要な検査です。チェック項目に沿って、運転者の身体機能や性格の特性を評価することを目的としています。教習生が安全運転の技術を効果的に学ぶために重要な検査で、一部は入校条件としても使用されます。
教習所の適性検査には、『運動能力検査』と『運転適性検査』の2種類があります。合宿免許では、入校初日に適性検査が実施されるほか、入校手続きや指定書類の受付、最初の技能・先行学科教習も行われます。
ここからは、運動能力検査と運転適性検査について具体的に説明します。
運動能力検査

基本的な身体機能のなかでも、運転に最低限必要な機能に焦点を当てて、視力(深視力)、識別能力、聴力、運動能力の4項目の機能が十分に備わっているかを確認します。項目と条件は普通車の車種(MT車、AT車)共通であり、結果が基準を満たしていない場合は入校できないこともあります。
1.視力(深視力)検査
視力検査において、以下の条件が求められます。
- 両眼7以上
- 片眼3以上
- 片眼が3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上であること
- 深視力検査に合格すること
眼鏡やコンタクトを使用する方は装着した状態で検査するため、自宅を出発する際に忘れないように事前に準備しておきましょう。
2.聴力検査
聴力検査において、以下の条件が求められます。
- 日常会話を聴取できること
- 両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器が聞こえること
聴力検査では、聴覚が交通の音や警笛にどの程度対応できるかをチェックします。聴力に問題がある方は、補聴器の使用が認められる場合があります。
3.色彩識別能力検査
赤色・黄色・青色の識別ができることが必要です。色彩識別は、信号機の色や標識の違いを見分けられるか否かに大きく影響するため、運転免許を取得するには必須の機能です。
測定結果が基準を満たしていないと入校できません。
4.運動能力検査
運動能力検査は、運転時の基本的な動作能力を確認する検査です。自動車の運転操作に支障を及ぼすまたは交通事故につながるような運動能力(四肢または体幹の機能)の障がいがないことが求められます。
障がいがある場合でも、補助手段で対応可能であれば教習を受けられます。
運転適性検査
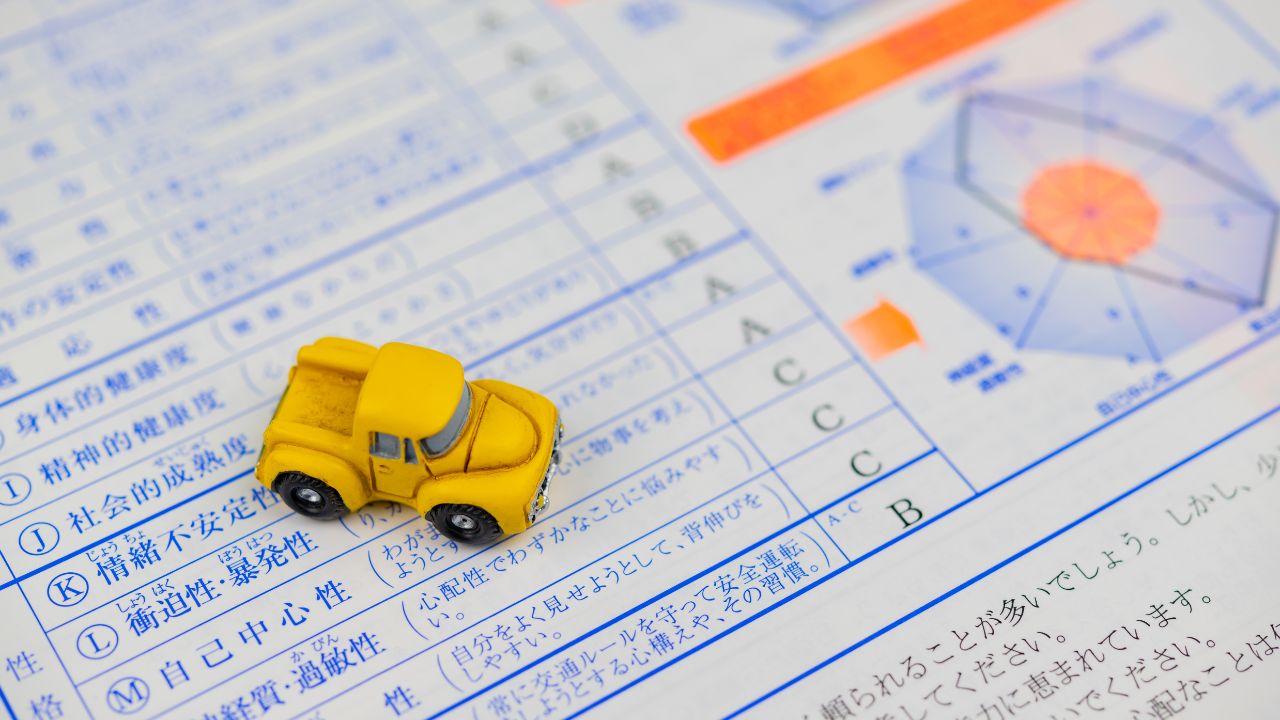
運転適性検査では、一つひとつの項目に対して回答していく質問形式で行われます。
運転者の性格や行動パターンを分析し、安全運転に適した気質を持っているか、リスク回避能力がどの程度あるかといった判断をするテストです。
1.警察庁方式K型
動作の正確さ、動作の速さ、精神的活動性、衝動抑止性、情緒安定性の5要素を中心に検査することで、自動車事故と関連性の深い運転傾向を分析し、安全運転に必要な適性を確認します。
検査形式は、マークシート式テストと『はい』『いいえ』で答える心理分析テストがあります。
検査結果は、教習生本人に通知されるだけでなく、検査結果に基づいて教習生一人ひとりに対する教習所での指導にも活用されます。
2.OD式安全性テスト
多くの自動車教習所で採用されているテストです。運動機能、健康度・成熟度、性格特性、運転マナーという4つの項目の評価に基づいて、それぞれ5段階で判定します。
検査形式は、おもに自分の考えに合ったものを『はい』『いいえ』で答えるマークシート方式で、心理テストのような感覚で進められます。
運転適性検査の診断結果で確認できる運転タイプ

検査結果から具体的にどのような内容が判明するのでしょうか?
ここからは、警察庁方式K型とOD式安全性テストの2つの検査から確認できる運転タイプを説明します。
1.警察庁方式K型
警察庁方式K型から分かる運転タイプは、以下の6つに分類されます。
| 運転タイプ | 特徴 |
| 状況判断が遅い人 | ・情報処理速度が遅く、周囲の状況を判断するのに時間がかかる傾向にある
・飛び出してきた歩行者や急ブレーキなどの突発的な対応が遅れる可能性がある |
| 動作は早いが正確さに欠ける人 | ・素早い反応が得意
・注意不足や確認不足により、急いでハンドルを切ったり、信号をよく見ずに通過したりするなどのミスが多い傾向にある |
| 神経質な傾向がある人 | ・細かいことを気にしすぎたり、過度に慎重になったりしやすい
・常に緊張状態にあり、頻繁にブレーキを踏むなど、無駄な運転動作が増える傾向にある |
| 気分の変わりやすさやムラがある人 | ・感情の起伏が激しく、集中力や注意力が安定しにくい
・気分の良し悪しで運転の質が変化する可能性がある |
| 攻撃的な傾向がある人 | ・他人を敵視しがちで怒りっぽい性格
・車の割り込みや煽り運転、クラクションを多用するなどの攻撃的な行動が見られる傾向にある |
| 自己中心的な傾向がある人 | ・自分の都合を優先しがちな性格
・他車や歩行者を無視した運転をする可能性がある |
これらのタイプは、運転時の注意点や改善点を知るために役立ちます。
2.OD式安全性テスト
OD式安全テストでは、運転適性度と安全運転度を組み合わせて診断します。運転タイプは以下の4つに分類されます。
| 運転タイプ | 運転適性度 | 安全運転度 | 特徴 |
| 安全運転タイプ | 高い
(5~3) |
高い
(A~C) |
安全運転への意識が高く、技術も高い |
| もらい事故傾向タイプ | 低い
(2~1) |
高い
(A~C) |
安全運転への意識は高いが、技術的なミスで追突事故などに巻き込まれやすい |
| 重大事故傾向タイプ | 高い
(5~3) |
低い
(D~E) |
技術は高いが、安全運転への意識が低く、重大な事故を起こす可能性がある |
| 事故違反多発傾向タイプ | 低い
(2~1) |
低い
(D~E) |
技術も安全運転意識も低く、事故や交通違反を繰り返す可能性が高い |
これらのタイプは、ドライバーとしての運転技術や判断力の資質という面だけでなく、安全に運転する能力や意識の高さについても評価されます。
適性検査の結果が良くないと入校できない?

適性検査の結果が良くない場合、入校できるかどうかは検査の種類によって異なります。 以下、それぞれの検査について説明します。
1.運動能力検査の場合
運動能力検査の項目である『視力』『聴力』『色彩識別能力』『運動能力』は、運転免許を取得するための法的要件です。教習所の入校にはこれらの基準を満たすことが定められているため、クリアできない場合は入校できません。
2.運転適性検査の場合
運転適性検査は、試験ではなく免許取得に直接影響を与えるものではないため、検査結果が良くない場合でも入校可能です。
ただし、特定の運転タイプでは、教習所において特別な指導が行われることがあります。
例えば、『重大事故傾向タイプ』では安全運転への意識を高めるための指導、『もらい事故傾向タイプ』では技術的なミスを減らすための指導など、検査結果に応じた指導を受けることで安全運転に必要な意識や技術を身につけられます。
運転適性検査結果の活用方法

運転適性検査の結果は後日受け取ることができます。 診断書の内容を確認し、自分の運転タイプを把握したうえで、今後どのように対処すべきかを考えましょう。
1.自分の運転タイプを知る
例えば、『重大事故傾向タイプ』と診断された場合、無意識のうちにスピードを出しすぎる、ほかのことに注意を向けやすいといった傾向があると考えられます。
スピードを出しやすいタイプなら、速度計をこまめに確認し、法定速度を守ることを意識したらよいでしょう。また、自分の行動パターンを知り、どのような場面でリスクを高めているのかを理解することが重要です。
2.安全運転への意識を高める
検査結果がどの運転タイプであっても、安全運転や危険を回避する意識を高めることは不可欠です。それぞれのタイプごとにリスクが異なるため、自分の特性に応じた改善を意識することが重要です。
例えば、『状況判断が遅い人』と診断された場合、判断の遅れが交通の流れを妨げる可能性があります。このようなタイプは、複数の情報を一度に捉えようとせず、落ち着いて判断できるよう意識的に視野を広げ、余裕を持って対応するとよいでしょう。
3.指導員からアドバイスをもらう
検査結果で不明な点があれば、指導員に質問すれば適切なアドバイスをもらえます。また、診断結果に対してどのように改善すべきか分からない場合にも、具体的な改善策を教えてもらうのも有効です。
アドバイスはすぐに実践することが大切です。自分では気づかない潜在的な気質やクセを知るよい機会にもなるため、自分自身を理解し克服につなげることを意識しましょう。
運転適性検査の結果が悪くても落ち込まないことが大切!

運転適性検査がすべてを決定するわけではありません。 そのため、結果が思うように良くなかったとしても、必要以上に落ち込む必要はありません。
大切なのは、検査結果をもとに改善点を意識し、運転に活かしていくことです。 診断結果を“改善すべき課題”や“自分の運転を見直すきっかけ”と捉え、前向きに受け止めましょう。
適性検査で自分の運転タイプを理解し安全運転の意識を高めよう!
合宿免許の適性検査は、安全運転に必要な身体能力の確認と、自分の運転のクセや傾向を知るために実施されます。
運動能力検査は基準を満たす必要があるため、眼鏡・コンタクト・補聴器・補助手段などを事前に準備し、入校当日に忘れずに持参しましょう。
一方、運転適性検査は、自分の運転傾向を知り、自己理解を深める良い機会です。 入校の合否には影響しないため、リラックスして検査に臨みましょう。




